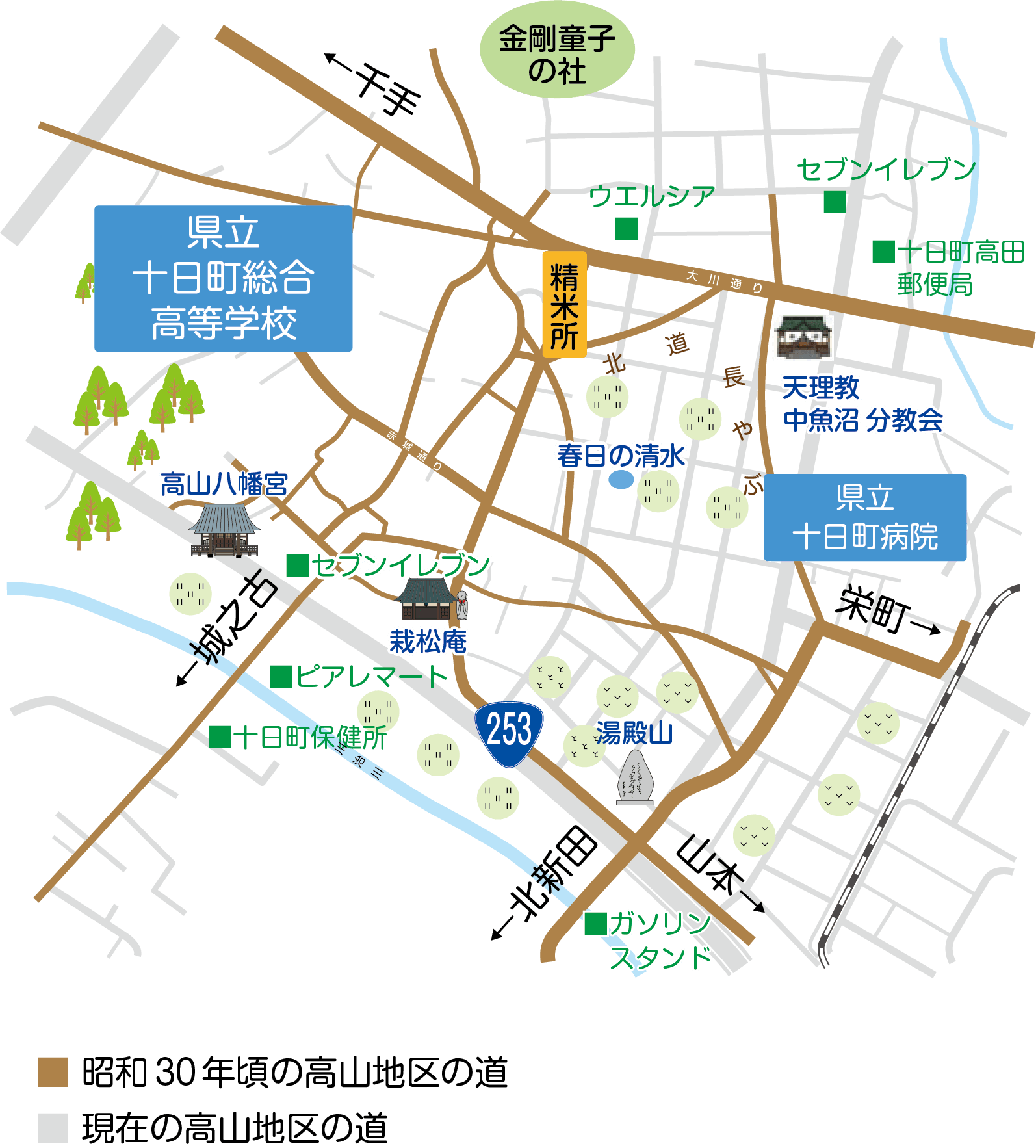高山の魅力
日本一の大河、信濃川。
十日町市は、中心部を信濃川が流れ、
両岸の雄大な河岸段丘の上に町がつくられました。
高山地区は、信濃川東岸にあって、
十日町市街地に隣接し、西側は信濃川に接しています。
また、幹線道路沿いには大型店などの
商業施設が集積していて、車や人で賑わっています。
地区内には保育園や高校などの文教施設があり、
県立十日町病院が隣接しています。
住宅地と商業地のバランスがとれ、文教施設や
病院が近くにあるなど、利便性が高い地域です。
高山の歴史
江戸時代後半の高山は幕府の直轄領で会津藩の預かりでした。
明治維新後、慶応4(1868)年には、高山村は柏崎県に属していました。その後、何回もの制度の変更や県の合併があり、明治6年に新潟県に属するようになりました。
明治12年に郡制度が発足して中魚沼郡ができたとき、高山村はこれを構成する82か村の一つでした。

信濃川の渡し舟

昭和のたかきや

高菊織物(2)
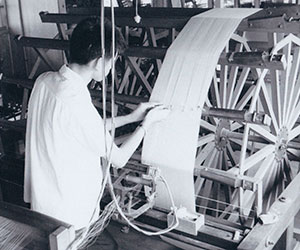
高菊織物(1)
当時の高山村は、現在の高山地区の区域のほかに「城之古分」が含まれていました。明治21年の町村合併で高山村(城之古分を除く)、山本村、八箇村が合併して「河内村」が生まれました。さらに、河内村は34年に川治村と合併して「川治村」になりました。
この時の中魚沼郡十日町、中条村、川治村、六箇村は、昭和29(1954)年の町村合併で十日町市が誕生するまで続くことになります。
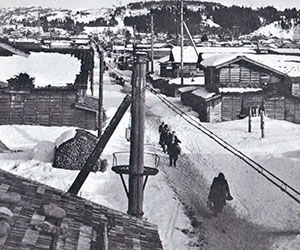
雪の高田町4丁目

三嶋屋商店

野沢菜洗い

田植えの一休み
令和の高山地区
現在の十日町市は、平成17年の4月1日に十日町市、川西町、中里村、松代町及び松之山町に5市町村が合併して誕生しました。
「高山地区」は市町村が合併などによって自治体は変わっても、旧高山村に暮らす人々の生活のまとまりとして生き続けています。
高山地区は、昭和30年代の高度成長期を迎えると人口の流入が続き、令和の現在は、800世帯約2000人が暮らし、幹線道路沿いに100を越す事業所が立地する地域となりました。
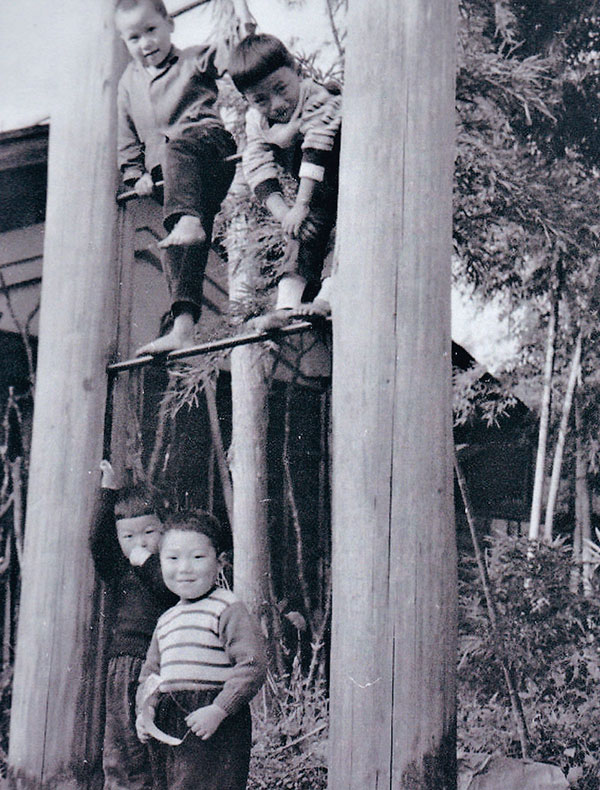
昭和の子ども達
生活に寄り添う町